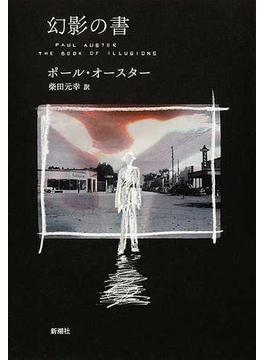「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発行年月:2008.10
- 出版社: 新潮社
- サイズ:20cm/334p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-10-521712-9
紙の本
幻影の書
絶望の危機から救ってくれた、ある映画の一場面、主人公はその監督の消息を追う旅に出る—大胆で意表を突くストーリー、壮絶で感動的。アメリカでもオースターの最高傑作と絶賛された...
幻影の書
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
絶望の危機から救ってくれた、ある映画の一場面、主人公はその監督の消息を追う旅に出る—大胆で意表を突くストーリー、壮絶で感動的。アメリカでもオースターの最高傑作と絶賛された長編。【「BOOK」データベースの商品解説】
絶望の危機から救ってくれた、ある映画の一場面。主人公はその監督の消息を追う旅に出る−。大胆で意表をつくストーリー、壮絶で感動的。アメリカでオースターの最高傑作と絶賛された長編。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
ポール・オースター
- 略歴
- 〈ポール・オースター〉1947年ニュージャージー州生まれ。コロンビア大学卒業。石油タンカー乗組員、山荘管理人などの職を転々としながら翻訳、詩作に携わる。「ニューヨーク三部作」で小説家となる。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
映像作品を文章で語ることの難しさを易々と超えている(読んでいてカット割りさえ浮かんでくる)。でも、それだけではない。
2009/01/27 21:42
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yama-a - この投稿者のレビュー一覧を見る
読み始めてすぐの時点での感想は、オースターはここ何作かで昔みたいな夢のような描写を失ってしまったのではないか、ということだった。
「夢のような」というのは「素晴らしい」という意味ではない。夢の中に出てくるような、個々の人間の姿はくっきりと見えているのに背景が何も描かれず空白になっているような、あるいはそれとは逆に、背景は細部に至るまで細かく描かれているのにそこにいる人間たちは目鼻さえはっきりしないような、別の喩えをするならばある種漫画の手法のような描き方である。
初期の作品と違って、ここ2~3作ではそういう印象を受けることがとても少なくなってしまったような気がする。にべもない表現をすると、オースターは「ファンタジーよりもリアリズムのほうに傾いてしまった」のではないか、という懸念である。でも、読んでいるうちにそんな手法の違いなんてどうでも良くなってしまった。
最愛の妻と子供たちを飛行機事故で亡くした大学教授のデイヴィッド・ジンマー(小説は彼の一人称で語られる)は死んだも同然の暮らしを送っていたが、ある日たまたまTVで見た無声映画に魅かれ、その監督でありコメディアンであり、ある日突然失踪してしまったヘクター・マンの遺作を順に追うようになる。そして、それは1冊の研究書となって世に出るのだが、その本を書くうちに彼の疲弊した心も次第に平静を取り戻して行く。
そんな折にヘクター・マン夫人だと名乗る人物から手紙が届き、ヘクターが会いたがっているので来てほしいと言う。
もちろん俄かにそんなことを信じる気にもならずぐずぐずしていると、今度は拳銃を持った女が無理やりにでも彼を連れ出す気でやって来た──前半はそんな話だ。ストーリーはヘクターの妻から手紙が届くところから書き起こされている。
そして、そこから先はさながらミステリ小説だ。その先がどうなるのか知りたくてどんどん引き込まれて行く。この辺はいつも通りのストーリー・テラーぶりとも言えるのだが、いや、この作品ではワンランク上がったような気がする。
そして、もうひとつ驚くべき点は、小説の中で細かく描き出されるヘクター作の映画である。訳者・柴田元幸のあとがきに「映画を細部まで詳しく語るときの筆の冴えっぷりは、映画作りの現場に身を置いてきた体験がもっとも実りある形で活かされた結果にほかならない」とあるのを読んで、ああ、そうか、そうだった、彼は映画の脚本や監督まで手掛けたのだと思い出した。
映像作品を文章で語ることの難しさを易々と超えている(読んでいてカット割りさえ浮かんでくる)だけではなく、その作中作で語られる映画のストーリーや設定が、時々登場人物の性格や行動や、あるいは偶然の出来事とシンクロしてくる辺りがものすごく面白い。
ともかくこんなに巧い作家だったかな、オースターって、というのが最後まで読み終えて一番強く思ったことだ。いや、前から確かに設定も筋運びも巧い作家ではあった。だが、構成においてここまでの力量を感じさせる作品は今までなかったのではないだろうか。
ストーリーが大方収束したなと思ったところからまだ20~30ページ残っていると気づいたとき、ああ、ここからジンマーにとって何か良くないことが起こるのではないか、と胸がザワザワしてきた。その予感が当たったかどうかはここには書かない。自分で読んでほしい。
いつも深い読後感があるオースターだが、ここ何作かの中では特に深い気がする。
by yama-a 賢い言葉のWeb
紙の本
あと24時間で、あなたが一番読みたかった本を燃やします。
2009/01/11 14:14
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:和泉潤 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「あと24時間で、あなたが一番読みたかった本を燃やします。」
そういう脅迫を突きつけられたらどうしますか?私はすごく困る。この主人公もすごく困った。燃やされるかもしれない作品は、小説ではなくて、ヘクター・マンという音の無い時代の映画俳優の映画だ。その俳優は半世紀前に謎の失踪をとげていて、作品自体も世界に散逸しているので、見るだけでも大変な労力とお金がかかる。それでも主人公は見てきた、飛行機事故で死んだ家族の保険金を湯水のように使って。世界中に散らばったフィルムを見て、論文を発表する。そうしたら雨の夜に突然きた女が、あなたに銃を突きつけて言うのです。「実は彼はまだ生きています、ですがもうすぐ作品を燃やします」と。
書評を読んでくれるような方や、私は、大分やられてしまっているのだと思うのだけれど、本や映画や、とにかく自分の内面でぶずぶず燃えて自分を食い尽くすような、そういうメディアに取り憑かれてしまう人間は、なんでこんなに、似たような人たちなんだろう。そして、なんでこんなに共感を持てるのだろう。私は彼ほど、孤独でも有能でもないのに。その作品に対する飢えのようなもの、知識に対するそれを知らなければ、届かなければ生きていた意味が無いと思えるほどの、この飢餓のような気持ちはいったいなんだろう。この作品ではそれが語られ、それがあと一歩、というところで手をすり抜けてゆく。一歩と言うより、前髪に触ったくらいの感触はある、それがまた、切ない。
紙の本
大きな後悔の物語
2009/01/10 07:55
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:羊男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
IT業界ではよく人がいなくなる。
あまりの激務に「消失」したり、行方不明になったりなするのだ。
昔、私が努めていたプロジェクトで「消失」したエンジニアが居たのだが、ひょっこりと帰ってきた。
どこに行っていたのか聞くと、鳥取砂丘でずっと砂つぶを見ていたという。
オースターの新作は、「失われた映画」を探し当てていく物語、といってよいのだろうか。
主人公の大学教授ジンマーは、その監督の消息を追う旅へ出る。
失われた映画監督ヘクターとフリーダ、ヘクターの伝記を書いた主人公とアルマの人生がクロスオーバーしていく物語といえばよいか。
実際の出会いではなく、物語の視点でのみ得られる四つの人生を重ねあわせた閉じた世界であり、その表象である言葉の世界。
これまでのオースターの小説とは何かが変わっている。
ひどく内省的な小説となったこれは哲学的なエッセイに近いものなのか。あるいは詩集「消失」の小説化といってよいのか。
個人の内奥をなるべく嘘の無いように、努めて静かに、間違いの無いように、あるいは書き落としたことがないように、その切り取った時空間の断片を、薄いガラス器のように丁寧に取り扱っている。
主人公の人生を通して、家族の死というものを、突き詰めて考え、自分が崩壊していくことを想像してみる。
その存在、事物の成り立ちについて、家族が失われた世界が現実において、起き得るべきあらゆる悲しみを想像してみること。
悲しみが、何なのかと考えてみることもなく、過ぎ去ってしまうこの人生と社会の流れの速さ。
なぜその慌ただしさに飲み込まれてしまわねばならないのか、既に起きてしまった悲しみを何度も何度も再現し、そのたびに後悔する。
そのたびに有り得ない選択肢を考え、その可能性を考え続け、後悔を続ける。
その人生の選び取り方、まるでそれが「自分」だとでも諭しているかのようでもある。
この物語の舞台になっている砂漠には、乾いた現実と失われた故郷や記憶しかない。
それは日野啓三が「砂丘が動くように」で表現したような湿った鳥取砂丘の孤独ではない。
社会とのつながりを確認するような孤独ではなく、他人とのわずかなつながりしか呼応しようのない、砂丘ではなく、砂漠としか言いようがない、ひどい世界なのだ。
たとえばそれは
「すべて本当であり、だがすべて虚偽でもある。センテンス一つひとつが嘘だが、言葉一つひとつが本心から書れていた」
といった内省的な文章がそれこそ一つひとつ積み重ねられている。
普段、私たちはそのときどきの思いや考え、そこに至る小さな決断といったものを意識せずに行なっている。
ひとつの結論に至るまでを言葉で表わそうとすれば、まどろこしくてややこしくて、お手上げになってしまう。
それをオースターはひとつひとつ文字を言葉を積み上げていく。
そういえば、レンガをそれこそひとつひとつ積み上げて壁を作り上げる物語もオースターにはあった。
そうした地道な作業を行なわなければならない背景を作り出し、ひとつの舞台を作り上げるのがオースターはとてもうまいのだ。
紙の本
面白い、だが面白さをこえたものがある
2010/03/14 21:40
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:本を読むひと - この投稿者のレビュー一覧を見る
久しぶりに小説を読むことの圧倒的な凄さを感じた。サスペンスはたんにエンターテインメントのそれではない。奇妙な不可解さに終始つきまとわれ、それは面白さを越えた何かの存在を想像させた。
映画、それも虚構の映画や監督、俳優が描かれているという点で、この小説はセオドア・ローザックの『フリッカー、あるいは映画の魔』と比較されるかもしれない。実は「小説のなかの虚構の映画」というテーマを追って『フリッカー』を読んでいたのだが、中途で挫折し、本書も読もうかどうしようか迷っていた。
だがある夜、睡魔におそわれながらも最初の1章を読んだ私は、眠りにひきずりこまれるなかで、この小説を最後まで読むことになるのをひそかに確信した(気がする)。
続く2日間のなかで『幻影の書』は一気に読まれたが、なめらかな、よくこなれた訳は自然に作品世界にいざないながら、この本に作者がこめたものは、そこかしこで棘のようなものを私のなかに残し、罠のようなものを私に仕掛けたと思う。
この小説の語り手「私」、つまりこの本自体を書いた当人とされているデイヴィッド・ジンマーの生と、彼がその生の奈落のなかで究極の関心をもち、その関心のなかで生をささええたサイレント期の喜劇俳優、監督であるヘクター・マンの生。
その二つの生には多くの重ねあわされるものがある。まず災厄があり、それによる止むことのない死にたさが二人にはある。もっと具体的なことでいえば、ジンマーが妻と二人の子供を失ったように、マンも妻になりそびれた一人の女と、二人の彼の子供を失う。つまり女の胎内にいた子供と、後にニューメキシコで蜂に刺されて死んだ2歳の子供と。
災厄後のジンマーに残された不本意な巨額の保険金と、災厄から失踪し続けたマンが遭遇し、結婚するフリーダの財産にも共通するものがある。
だがマンにおける新しい女フリーダと、ジンマーの前に登場した新しい女アルマに共通するものはあるのか、と問えば、そこには悲痛なほどの落差があり、それは終盤のサスペンスにおいて明らかになる。
災厄後にジンマーは『ヘクター・マンの音なき世界』を著わし、シャトーブリアンの訳書は完成できなかったようだが、この自らの生を描く『幻影の書』を書きすすめた。マンは子供の死という新たな災厄後にニューメキシコで14本の映画を撮り続けたが、そのなかの1本『マーティン・フロストの内なる生』のみが、ここでは迫真の描写によって詳しく紹介される。
異なったレベルの「作品」がある。シャトーブリアンの長い自伝は現実に存在するが、ジンマーによるマンの映画の研究書も、そのマンによる映画も虚構の存在である。一方、ジンマー自身が書いたとされるこの『幻影の書』は、そのこと自体は虚構だが、作者自身の小説という意味では現実に存在する。その二重の意味において、『幻影の書』はたんに現実のものでも、たんに虚構のものでもない。
また「作品」へと結実しない虚構の書かれたもの、たとえばマンがつけていた日記のようなものもある。
ニューメキシコに招かれ、アルマの部屋でたまたま「私」が手にしたマンの日記の一部分には、マンたちが住んだブルーストーン農場の名前のもとになった(と「私」が思う)エピソードが綴られているが、そこには小説の本筋とは全くかかわりのない不気味に凝縮された短編の味わいがあり、これも「作品」なのかもしれない。
こうした虚構のなかの虚構の奇妙な迷路の感覚において、この小説にはボルヘス的なものがあるが(ヘクター・マンはボルヘスと同じアルゼンチン出身に設定されている)、ただ徹底した細部へのリアルな視線と描写において大いなる開きがある。
小説の最終部において、マンの妻フリーダによるマン死後の理不尽とも思える行動(それはアルマを通して「私」に伝わる)は不可解な刺激をもたらすが、フリーダを造型するにあたって作者は、同じニューメキシコにD・H・ローレンス(訳が「ロレンス」ではないのが、いい)と暮らしていた妻フリーダを想起させることを見込んでいたかもしれない。
小説の9つの章のうち、最も長い5章全体は、ニューメキシコへの飛行機のなかでアルマがジンマーに語ったマンのその後だが、ここにはやがて失われることになるアルマによるマンの未完の伝記が別のかたちで存在している。これが全体の4分の1か5分の1。
それに対して2章の全体は、ジンマーによる失踪以前のマン作品論を、ジンマー自身が要約したものと言えるだろう。25ページを要して『ヘクター・マンの音なき世界』が変奏されているのだ。
また5章に次いで長い7章は後半ほとんどがマンの残された映画の一つについての目を見晴らす描写によって成立しているが、こうした作品内作品や物語、挿話の無理のない埋め込み方に感嘆せざるをえない。私は無理ある埋め込み方をする、たとえばドストエフスキーの長編などを思い浮かべた。
この小説には尋常のものとはいえないサスペンスがあるが、それは消費的な昂奮やこころよさと異なる。何か生きることのサスペンスに繋がりがありそうな気がするが、的確に言いあらわせないのがもどかしい。芸術のサスペンス、という言い方では何となく誤解されそうだ。たとえば本を読み、映画を見ているこの何気ない生のかたわらに潜む奈落、さらにその奈落の先にあるもの、そうしたものを作者は描こうとしたのだろうか。
むしろオースターは書きながら、ひそかにこう呟いていたのかもしれない。『幻影の書』を書きつつある、そうした行ないもまた一瞬のうちに不可能になりうるのが人間であり、そして世界なのだと。
そしてもっと重要なのは、描かれた小説の豊かで明確な細部、錯綜する時の往還の正確な調節、時代をあらわすものへの巧みな配慮、つまりこの小説そのものだ。
毎年選ばれるミステリー小説の投票で2008年の海外小説のうち、1位にトム・ロブ・スミスの『チャイルド44』が選ばれ、本書はベストテンに入ってはいない。
私は『チャイルド44』を面白く読んだが、そのサスペンスはジェットコースター的な昂奮に類するもので、今回『幻影の書』で味わいえた(かに思わせた)面白さとは違う。
『チャイルド44』の面白さは作者の続く作品を私に読ませ、少し落胆させたが、たぶん初めて読んだのだと思うポール・オースターがこれから私にとって、どのような作家になるのだろうか自問している。
紙の本
物語を紡ぐ力
2008/11/24 14:40
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:katu - この投稿者のレビュー一覧を見る
飛行機事故で家族を失ったデイヴィッド・ジンマー。彼を失意の底から救ったのは一編の無声映画だった。その映画の監督であり、脚本家であり、主演であるヘクター・マンなる人物は謎の失踪を遂げ、既に死んだと思われていた。デイヴィッドはヘクターの足跡を追ううちに彼の数奇なる人生を知ることになる。そして、デイヴィッド自身がヘクターの運命に関わることになる。
とにかくヘクター・マンの人生があまりにも波乱に富んでいて実に読ませる。全ての物語は巧妙な入れ子構造になっており、デイヴィッドはヘクターの人生を生き、我々読者はヘクターのそしてデイヴィッドの人生を生きることになる。
ポール・オースターの物語を紡ぐ才能は本当に素晴らしい。そこら辺に転がっていそうな話を「あるよね〜、そういう話」という風に仕立て上げているのとは訳が違う。「無」から「有」を紡ぎ出し、あり得そうもない話に息吹を吹き込み、登場人物たちに存在感を与え、読者の胸を打つ「おとぎ話」を作りあげる。
柴田元幸の解説を読むと、嬉しいことにこのあとに発表された作品も本書と同等以上の水準を保っているらしい。今から読むのが楽しみだな。
紙の本
やっぱ、最高傑作ではないでしょう。これが最高傑作であるならば、オースター自身が大した作家ではないことになってしまいます。正直、昨年翻訳された海外小説にはもっといいものが多かった、私はそう思います。
2009/05/25 21:07
11人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
どうも苦手なんです、オースター。柴田元幸の訳も含めて悪く言う人はいない。現代アメリカ文学の最高峰とも言われています。だから何度か挑戦したんですが、J・アーヴィング作品を読むような楽しさを感じないんです。『偶然の音楽』も『リヴァイアサン』もダメでした。でも、出版社のHPに
救いとなる幻影を求めて――オースターの魅力のすべてが詰め込まれた最高傑作長編!
妻と息子を飛行機事故で失うという人生の危機の中で、生きる気力を引き起こさせてくれた映画の一場面。主人公はその監督ヘクターについて調べてゆくことで、正気を取り戻す。ヘクターはサイレント時代末期に失踪し、死んだと思われていた。しかしある女性から実は生きていると知らされる……。意表をつくストーリー、壮絶で感動的な長編。
なんて書かれると、もう一度挑戦するか、って思うんです、なんたって「オースターの魅力のすべてが詰め込まれた最高傑作長編!」です。他のところにも「アメリカでもオースターの最高傑作と絶賛された長編」とある。出版社だけじゃあなくて、第三者も絶賛です。ま、今までのオースター作品だって、そうだっていや、そうだったんですが・・・
でもねえ、このタイトル、何とかならなかったんでしょうか。どうしてもジェフリー・フォード『記憶の書』と勘違いしちゃうんですけど。じゃあ、THE BOOK OF ILLUSIONS を他にどう訳せばいいか、って聞かれても答えられない私ではあるんですが。ま、The Physiognomy を『記憶の書』、って訳すほうの問題もあるんですけど。でも、いいタイトルではあります、二つとも。
それとカバーのインパクト、これも両者譲りません。黒を基調にしたストイックでアーティスティックな大塚いちおの装画の『幻影の書』に対して、色が弾けるような華麗でファインアート風の『記憶の書』。ただし、本の造りそのもので言えば、新潮社装幀室の『幻影の書』より『記憶の書』のほうが上かな、値段もあるかもしれないけれど・・・
閑話休題。で、読みました。印象ですが、J・アーヴィングと大江健三郎の作品を思い浮かべました。アーヴィングであれば『サーカスの息子』『また会う日まで』、大江ならば『取り替え子 チェンジリング』『憂い顔の童子』『臈たしアナベル・リイ総毛立ちつ身まかりつ』。映画を扱っている、それだけって言えばそうなんですが、ミステリタッチなところも似ています。
それとベルンハルト・シュリンク『帰郷者』、リチャード・パワーズ『われらが歌う時』です。こちらは小説と歌が扱われるのと戦争や人種差別がテーマなので、そういう意味では違うんですが、なんていうかミステリタッチのところと、そのために時代を遡る、その様子と文体が、明らかにエンタメのものとは違って、重厚なんです。
正直、私にとっては『幻影の書』が、これらを越える、とは思えません。ま、以下でもない。互角かちょっと下。理由は主人公であるデイヴィッド・ジンマーに魅力を感じないこと。ま、私は総じて大学の先生に魅力を感じないんです。世間知らずで、人間関係をつくることが下手。身内でまとまる、っていう潜入観があって、このハンプトンの大学教授もその域をでません。
彼のことを説明するのに一番重要なのは、1985年、36歳のとき、航空機事故で妻のヘレン、7歳の息子トッド、4歳のマーコを亡くしていることです。その傷はいまも癒えていません。あ、ここらはフランシス『審判』に似ているかも。愛する人を失う、っていうのは大変なことなんですが、それが子供たちも亡くなって、自分ひとりが生きている、となれば考えるだに辛いです。
そんなジンマーを惹きつけたのが、1929年に失踪したユダヤ人のコメディ俳優のヘクター・マンです。俳優をしていたころは、ハンサムぶりもあって派手な女性関係が有名で、12本の作品を残すのですが全てのオリジナル・フィルムが残っているわけではありません。その彼の貴重なテープが、ある時から世界各地の施設に寄贈され始めます。
マンのことを書いたジンマーの著作は1988年に完成し、評判をよび、出版されてすぐにジンマーのところにニューメキシコに住むマンの妻から「ヘクター・マンがいまも存命で、貴方に会いたがっている」と書かれた招待状が舞い込みます。しかし、その話はなぜか立ち消えになり、11年後の今になって・・・
既に書いたように、部分的に雰囲気が似た作品は数多くあります。特に、最近、そのての小説の出版が相次いでいるので、凄い、やった、という感動はありません。ただし、とても気に入ったエピソードがあります。それがスポーケンの繁華街にある〈レッド運道具店〉での恋物語です。恋、にも発展しなかった一挿話なのですが、これが突然ラスト近くになって浮上します。
消そうとしても消せないものがあるとしたら、それは若いときの恋の記憶。たとえそこで自分が傷つき涙したとしても、その思い出はいつまでも甘美でありつづけます。それは片思いでも、変わりません。いや、肉の交わりをもたなかった一方的な思いのほうにこそその傾向が強いのかもしれません。まして、それが唐突に終ってしまったものであれば・・・
やはり私にとって、面白いのはミステリの部分ではなく、恋愛の部分です。
紙の本
ブルックリンの四つ角でプカリ浮かんだジタンの煙
2009/05/04 20:25
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あまでうす - この投稿者のレビュー一覧を見る
この人の本は「偶然の音楽」以来2冊目になる。前作も良かったが、こちらのほうが一段と読み応えがあった。
何といっても映画「スモーク」の原作者・脚本家だけに、ストーリー自体が抜群に面白い。映画的だ。
愛する妻子の突然の事故死からはじまって、無声映画の最後の巨匠との思いもかけない邂逅、そこで明かされる巨匠の生涯の秘密、そして主人公の前に現れた運命の女性アルマとのたった8日間の凝縮された愛、そしてなおも巨匠の最後の作品と死をめぐって最後まで残された黒い疑惑、シャトーブリアンの膨大な回想録からの気の利いた引用、(「人間はひとつの生を生きるのではない。多くの、端から端まで置かれた生を生きるのであり、それこそが人間の悲惨なのだ」)、本編に挿入されて実際に映画化された「マーチン・フロストの内なる生」のシナリオの素晴らしさ等々、これは第1級の娯楽読物であり、優れた人生の書でもある。
とりわけ喜劇俳優や若い女性、ポルノ女優、小人、大学教授などのインテリゲンチャなどそれぞれの人物像の水際立った造形とディテールの精密な押さえ方は見事なもので、この1947年ニューアーク生まれの若い作家の才能は底知れない、というべきだろう。
ニューヨークの街角のドラッグストアを舞台にハーヴェー・カイテルとウイリアム・ハートが主演したウエイン・ワン監督の「スモーク」もいかにも都会的で洒落た映画だった。ラストでゆっくりと立ち上る煙草のけむりのはかなくも美しかったこと。確か共同プロデューサーには独文の堀越君が参加していたっけ。ああいうユーモアとエスプリがきらりと光る映画を目にしなくなってひさしい。さびしいことだ。
♪ブルックリンのドラッグストアの四つ角でプカリ浮かんだジタンの煙よ 茫洋
紙の本
自己中心的な、余りにも自己中心的な
2008/12/16 14:07
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:石曽根康一 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ある日、世界は崩壊しました。
それは主観的観点からでしょうか?
おそらく、ポール・オースターは、世界の崩壊は主観的なものと考えるでしょう。
『幻影の書』は世界が崩壊した状態から始まり、
再生しかけ、クライマックスがあり、別のあり方で再生するという物語です。
具体的に世界が崩壊した状態というのは、主人公にとっては、妻と子供を飛行機事故で亡くしたことであり、彼は酒におぼれるわけです。
その一個人を物語は固定カメラで映しているかのようにずっと見つめていく。
それは「ていねい」だとか、「密度が濃い」という言い方もできるでしょうが、僕にはひどく個人的で、自己中心的だと思われます。
世界とは何でしょうか?
〈私の目〉から見たものが世界なのでしょうか?
物語の終盤に、主人公は、〈見えないものは存在しないのだ〉という考えを抱きます。
しかし、果たしてそうなのでしょうか?
なぜ、そんなに主観的に世界を捉えるのでしょう?
この本は映画が主題です。
ですから、〈見る〉という行為に力点を置くのはある程度しかたがないのかもしれませんが、しかし、主人公が視力を失ったら、どう感じるのでしょうか?
そのとき、世界は〈なくなる〉のでしょうか?
しかし、自己中心的な彼のことですから、今度は「触れないものは存在しない」とか言い出すのでしょう。
僕は以前、ポール・オースターのエッセイ集を読んでいて、ひどくアメリカ的で、個人主義的でいやになったことがあります。
『幻影の書』でも、出てくる人物たちは、主人公にとって何らかの意味を持った人物に限られ、プラス、マイナスの作用がなければ、存在しない、というように受けとめられます。
しかし、僕にとって、世界というものは自分が中心のものではありません。
僕は自分が知らないこと、見えないことが「ないのだ」と断言することはできません。
新潮社のつくったオビにはポール・オースターの「最高傑作」だと書いてありますが、首を傾げたくなります。
おそらく、彼はこのベクトルで進んでいくのでしょう。
あくまでも自己中心的に。
そして、それを喜んで日本の読者は受け入れるのでしょう。
1日1ドル以下で生活している人を見たことがないということで、その存在を黙殺しながら。